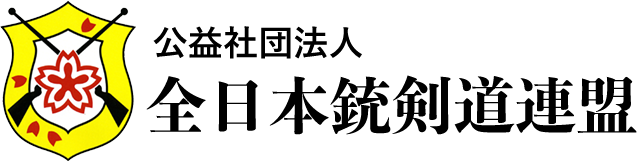短剣道とは
小太刀の技法を取り入れて研究され、正式化された「短剣術」を起源とする武道です。
昭和53年に全日本銃剣道連盟が再興させ、銃剣道とともに「車の両輪」として、普及・発展に努めています。
また、短剣道の大きな特徴として、相手の竹刀を持っている腕を押さえて突く「制体技」というものもあります。
服装
銃剣道衣に、剣道の防具のような銃剣道用具を着けて竹刀やなぎなたと同じように小太刀というものを持って行います。
短剣道の服装は、銃剣道衣と同じです。
剣道と同じように面・小手に対する「打ち技」と喉・胴に対する「突き技」のほかに、
相手と接近した瞬間に相手の腕をつかんで相手の動きを止めて突く「制体による突き技」で構成されています。
用具
-

-
- 竹刀(しない)
-
剣道の竹刀を短くしたもの。
長さ53cmで重さが成人用は250グラム、女子・18歳未満は200グラムで剣道と違って片手で持ちます。
- 短剣道用具
-
銃剣道の防具と同じ、『面』・『小手(右手のみ)』・『胴』・『垂』といったものに、
胸を保護するために胴の下に着ける『胸当て』という用具をプラスしたものです。
短剣道の試合方法

-
- 用具を着けた試合(小学5年生以上)
-
10メートル四方の正方形のコートで行います。
早く・正確に正しい姿勢で相手の胴または喉を突くか、面または小手を打って勝敗を争います。
また、短剣道の特色として相手の竹刀を持っている方の腕を上下に押さえて打突することも認められています。(制体技という)
銃剣道と同じく、3人の審判員が左胸・喉を突いた技を判定して、2人以上が一本と認めて同色の旗を挙げれば一本となります。
- 勝敗の決め方
-
制限時間内に二本先取した選手が勝ち。
制限時間が経過した場合、一本先取している選手が勝者となります。
お互いに一本ずつ取得または一本も取得していない場合は、『延長』『引き分け』『判定』のいずれかになります。(大会規則により異なる。)
- 一本となる有効突き部位
-
突き技
相手の胴を突く「胴(どう)」
相手の喉を突く「喉(のど)」
打ち技
相手の面を竹刀の先端3分の1の部分で打つ「面(めん)」
相手の小手を竹刀の先端3分の1の部分で打つ「小手(こて)」
制体技(せいたいわざ)
相手の竹刀を押さえたり、相手の技をかわすと同時に相手の竹刀を持っている腕を下に押さえたり、
上にあげるなどして、相手の体を制して突く。

-
- 基本技試合(小学4年生以下)
-
小学4年生以下は体の発達等を考慮し、用具を着けず、基本技の試合を行っています。
決められた基本技を横に並んで行い、姿勢や発声など総合的に優れている方を3人の審判員が判定し、旗の数が多い方が勝ちとなります。